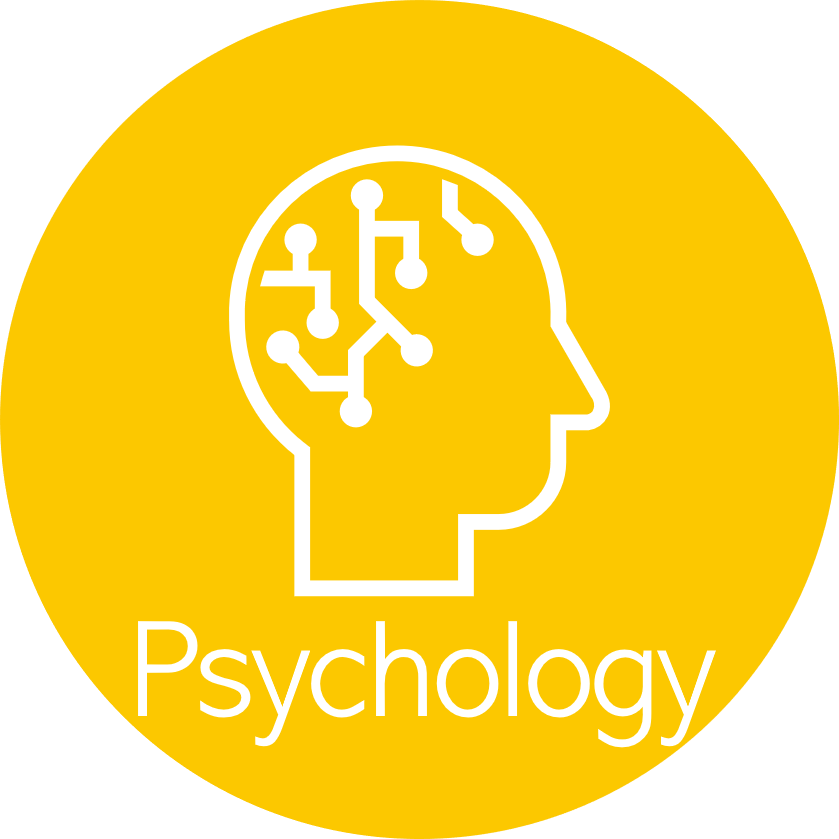学習目標
- 出生前の発達段階を説明し、出生前のケアの重要性を認識する。
- 乳児期から児童期にかけての身体的、認知的、情緒的な発達を評価することができる。
- 思春期に起こる身体的、認知的、情緒的な発達を比較対照することができる。
- 成人期に起こる身体的、認知的、情緒的な発達を検討する。
人は生まれてから死ぬまでの間、成長し続けています。
本章の冒頭で述べたように、多くの発達心理学者は、人間の発達を身体的発達、認知的発達、心理社会的発達の3つの領域に分けて考えます。エリクソンの発達段階を反映して、生涯発達は年齢に応じたさまざまな段階に分けられます。ここでは、胎児期、乳児期、児童期、青年期、成人期の発達について説明します。
胎児期の発達
あなたはどのようにして今の自分になったのでしょうか?一つの細胞から始まって、あなたが生まれるまでには、整然とした、そして繊細な順序があります。
胎児期の発達には、「生殖期」「胎芽期」「胎児期」の3つの段階があります。それぞれの段階で、赤ちゃんはどのように成長していくのかを見ていきましょう。
卵体期(1〜2週)
このコースの序盤の生物心理学の話では、遺伝とDNAについて学びました。母親と父親のDNAは、受胎の瞬間に子どもに受け継がれます。受胎は、精子が卵子と受精し、接合子を形成することで起こります(図9.7)。接合子は、精子と卵子が結合してできた1細胞の構造として始まります。この時点で、赤ちゃんの遺伝子構成と性別が決まります。受胎後1週間は、1細胞から2細胞、4細胞、8細胞と分裂・増殖していきます。このような細胞分裂の過程を有糸分裂といいます。有糸分裂はもろいプロセスで、最初の2週間を超えて生き残る接合子は全体の2分の1以下です(Hall, 2004)。分裂が始まって5日後には100個の細胞ができ、9ヶ月後には数十億個の細胞ができます。細胞が分裂すると、より専門的になり、さまざまな器官や体の部分を形成します。卵体期では、細胞塊はまだ母親の子宮の内膜に付着していません。付着すると、次の段階へ進みます。
胎芽期(3~8週)
接合子は約7~10日間分裂し、150個の細胞を持った後、卵管を通って子宮の内膜に着床します。着床すると、この多細胞生物は胚と呼ばれます。今度は血管が成長し、胎盤が形成されます。胎盤は子宮に接続された構造物で、母体から臍帯(へその緒)を介して成長中の胚に栄養と酸素を供給します。胚の基本的な構造は、頭部、胸部、腹部となる部分に発達し始めます。胎芽期では、心臓が鼓動を始め、臓器が形成されて機能し始めます。胚の背中に沿って神経管が形成され、脊髄と脳へと発達していきます。
胎児期(9~40週)
生物が9週目くらいになると、胚は胎児と呼ばれます。この段階では、胎児はインゲン豆くらいの大きさで、「尾」が消え始め、人間として認識できる形になってきます。
9〜12週目には、性器が分化し始めます。16週頃になると、胎児の体長は約4.5インチ(およそ11.4㎝)になります。指や足の指が完全に発達し、指紋も見えるようになります。生後6ヶ月目(24週)になると、体重は1.4ポンド(およそ635g)になります。聴覚が発達し、音に反応できるようになります。肺、心臓、胃、腸などの内臓が十分に形成され、この時点で早産した胎児が母親の子宮の外で生き延びる可能性が出てきます。胎児期の間、脳は成長と発達を続け、16週から28週にかけて約2倍の大きさになります。36週頃になると、胎児はほぼ出産可能な状態になります。37週目には、胎児のすべての器官系が発達し、早産に伴う多くのリスクなしに母親の子宮の外で生存できるようになります。胎児は40週頃まで体重が増え続け、体長も伸びていきます。その頃になると、胎児はほとんど動くことができなくなり、出産が間近に迫ってきます。図9.8に各段階の経過を示します。